エチレンは多くの製品の原料となる,工業的に非常に重要な物質である。また,二重結合を有することから様々な実験の基質となりうるため,教育的にも非常に魅力ある物質である。教科書では実験室的製法として,酸触媒に濃硫酸を使う合成法が紹介されている。しかし,生徒実験で扱うには安全上大きな不安がある。濃硫酸法に代わり徐々に広がっているのが活性アルミナを用いる合成法である。エタノールを含ませた脱脂綿を試験管に入れ,アルミナを入れて加熱するだけでエチレンが発生するという,非常に簡単な合成法である。しかし,副生成物としてジエチルエーテルが多くできてしまうという難点があった。アルミナの代わりに酸性の強いβゼオライトを用いると,ジエチルエーテルの副生を最小にしつつエチレンを得ることができる。
この実験は,生徒が安全・簡単に行うことができる。また,エチレンの合成および確認の実験を,50分の授業時間内で実施できる。さらに,目に見えなく理解しにくい気体の有機化学実験を,臭い,色の変化,燃焼時の変化など,五感をフル活用しながら楽しく学習できる,という特徴がある。
生徒は,中学1年の「気体の発生と性質」や,2年生の「酸化と還元」ですでに気体発生の実験を行った経験があるため,装置の組み立てや水上置換の操作などをスムースに行うことができる。こうした中学で実施した実験を導入に生徒を引きつけ,有機化学という新しい学習内容,ゼオライトという新しい物質をその上に積み上げることで,生徒の知識の定着はより確実なものになると思われる。
βゼオライトは,ホームセンターなどで購入できる根腐れ防止剤や調理用のゼオライトで代用できる。この場合は,塩化アンモニウムなどで陽イオン交換を行いアンモニア型とする。
実 験
<試薬>βゼオライト,エタノール, 0.01 %過マンガン酸カリウム(KMnO4)水溶液,臭素水(10 倍希釈)(可能であれば)
<器具>水槽,スタンド,クランプ,試験管(大,気体発生用,18 mm 程度×1),試験管(小,気体捕集用15mm 程度×4),気体誘導管付きゴム栓,ゴム栓,ガスバーナー,ガスマッチ,脱脂綿,ピペット,薬さじ
試験管の径は,標準的なものでこれ以外でも可。試験管(小)は,スクリューキャップのサンプル瓶の方が使いやすい。過マンガン酸カリウムは,硫酸酸性とする必要はない。
<手順>
(1) 必要数(4本)の試験管(小)とゴム栓を水に沈める。(今回は,サンプル瓶を使用)
(2) 試験管(大)の底に脱脂綿を入れ,エタノールを4 mL程染み込ませる。
(3) 試験管(大)口の部分をクランプで保持し,ほぼ水平にセットする。
(4) βゼオライトを,薬さじ(小)で二杯程(これで0.25 g程)試験管の中央部に入れる。
(5) 気体誘導管付きゴム栓を取り付ける。ゼオライト部を加熱し,発生する気体を集める。1本目には空気が混入しているので,実験には使わない。バーナーの火は,炎が試験管に触れない程度とする。気体の発生が遅い場合はエタノールの供給不足なので,脱脂綿の部分を暖める。
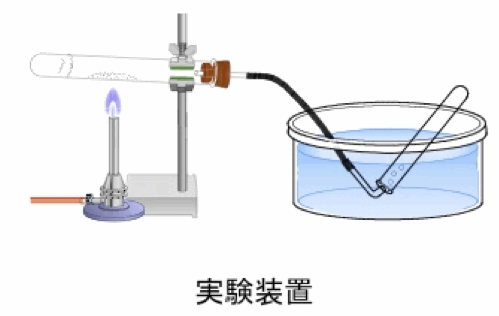
(6) バーナーの火を消した後,水の逆流を防ぐため,気体誘導管付きゴム栓を取り外す。
(7) 2本目の試験管に,駒込ピペットですばやく過マンガン酸カリウム水溶液(あるいは臭素水)を入れ,ゴム栓をし,振り混ぜて変化の様子を観察する。過マンガン酸カリウム溶液や臭素水を多量に入れるとエチレン不足となるので,注意が必要。
(8) 4本目の試験管を水平にしてスタンドに固定した後,ガスマッチの炎を試験管の口に近づけてからゴム栓を外して点火し,燃焼の様子を観察する。エチレンの比重は空気と同程度であるため,試験管から出にくく空気と混じりにくい。
演示実験として,3本目を採取した後に気体誘導管に乾燥したピペットをつなぎ,しばらく時間を置いて(ピペットの内部がエチレンで満たされる時間)ライターでピペットの先端部から出てくるエチレンに点火すると,オレンジ色の小さな炎を観察することができる。
参考文献 松橋博美,菊地友佳子,伊藤崇由,林 昭宏,理科教育学研究, 57(3), 293-300, 2017.
DOI:10.11639/sjst.15062