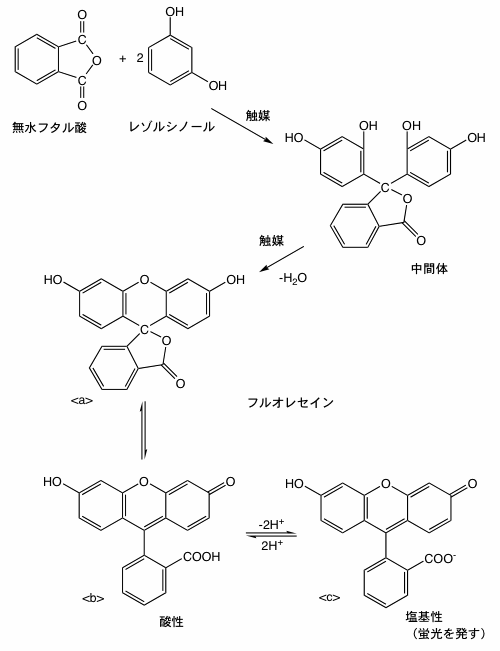〜色で見る触媒反応〜 蛍光色素フルオレセインの合成
ゼオライトは,濃硫酸にやや劣るくらいの強い酸性をもつ固体(固体酸)です。酸を触媒として起きる反応に,濃硫酸などの液体酸の代わりに用いることができます。この固体酸触媒を用いて,蛍光ペンの色素として利用されているフルオレセインを合成します。
実験室では・・・手で触っても皮膚を侵すことがないので,硫酸を使用するよりも安全に実験を行うことができます。色が変化する反応なので,分析装置を使わずに目で見て結果を確かめることができます。
環境化学として・・・工業化学の分野では,より環境に優しい反応プロセスへの変換に触媒技術が利用されています。固体酸触媒は,生成物との分離が容易であることや,廃酸処理が不要で廃棄物を減らせること,反応器を侵さないことなどから,硫酸等の環境負荷の高い酸触媒の代わりに用いられています。現在も様々な反応プロセスにおいて,液体酸から固体酸触媒への変換を目指して触媒開発が進められています。
蛍光色素フルオレセインの合成
【準備】
・βゼオライト(JRC-Z-HB150)
・無水フタル酸(乳鉢ですりつぶす)・レゾルシノール
・エタノール ・Na2CO3水溶液(1M程度)
・試験管(ガスバーナーでの加熱が可能なもの)
・試験管立て(金属製が望ましい,ビーカーで代用可)
・試験管挟み(金属製が望ましい)
・スパチュラ
・2mlピペット,ゴムキャップ
・ガラス棒
・ブンゼンバーナー,ライターかマッチ
・ブロックバス*1
・PCプロジェクタ*2
*1 アルミブロックに試験管を立てて温度制御ができる加熱器。使用温度範囲が200℃までのもので10〜15万円程度(製品名:ブロックバス,メタルバス)。オイルバス,砂浴で代用可。
*2 青色LED(一個100円程度)で代用可,白色LEDも使用可。なければブラックライト。
その他,反応時間を計るための時計かストップウォッチを用意すると良い。また,参加者は保護めがねとゴム手袋,あれば白衣を着用すること。
〈準備〉
・ブロックバスを120℃に設定しておく。(温度が安定するまでに,30分から1時間程度かかる)
・ブンゼンバーナーをガス栓に接続する。
注意:ブロックバスは,機器によって表示温度と実際の温度が異なる場合があります。ブロック部分に温度計用の差し込み穴がある場合には,事前に実際の温度が120℃になっているか確認してください。
〈1.触媒の活性化〉
ブンゼンバーナーをセットして点火する。
試験管にゼオライト(JRC-Z-HB150)をスパチュラで1杯入れ,バーナーで2分程度加熱する。加熱後,試験管立てに立ててさます。
・ゼオライトに吸着している水蒸気(とアンモニア)が発生し試験管がくもります。くもりがなくなるように過熱することがポイントです。
・良く乾燥してあるゼオライトではくもりが観察できない場合がありますが,加熱中にゼオライトがさらさらとしてくるなど変化がみられますので,注意深く観察してください。
・ガスバーナーの炎を直接見ると目を傷める場合がありますので,保護めがねを着用してください。
〈2.合成反応〉
試験管が軽く触れられる程度まで冷えたら,無水フタル酸を薬さじ(小)かるく1杯,レゾルシノールをしっかり1杯加え,これを120℃に設定したブロックバスに入れ,色の変化を観察しながら10分間ほど反応させる。
・試験管が冷えるまでには5分程度かかります。確認の際,やけどをしないように十分注意してください。
・反応を始めてすぐに赤褐色に変化する様子が見られます。上から覗き込まず,試験管を持ち上げて何度か観察してください。
〈3.合成物質の確認〉
10分たったら,試験管をブロックバスから取り出し,熱いうちにピペット(エタノール用)でエタノール2mLを加え,振って混ぜて溶かす。
空の試験管に1M Na2CO3水溶液2mLをピペット(Na2CO3用)で取り入れ,エタノールを加えた試験管から上澄みをピペット(採取用,新しいもの)で取って数滴加え変化を見る。
できた溶液を,PCプロジェクタの青色で照らしてみましょう。
・十分に冷めてからエタノールを加えると,生成物が凝固して溶けにくくなります。あまり冷えないうちにエタノールを加えてください。
・固体が試験管のそこにこびりついている場合がありますが,良く溶かしてください。全て溶けきらなくても構いません。
・Na2CO3水溶液を取り入れる試験管は,サンプル瓶・20mLビーカー等のガラス製小瓶で代用可能。
・エタノールで溶かしたフルオレセインをNa2CO3水溶液に加えると黄緑色に変色します。ここでの色が濃すぎると,LEDで照らした際に蛍光が見づらいので,透明感のある黄緑色になるように加える量を調整してください。

フルオレセイン合成は酸触媒を介して進む反応ですが,触媒がなくても高温で合成されます。実験では,温度制御に注意してください。また,触媒として濃硫酸を用いると,常温でもゆっくりと反応が進みます。
図のように,無水フタル酸とレゾルシノールの反応から中間体が生成し,さらに脱水されてフルオレセインになります。フルオレセインは,aとbの2つの形で存在しますが,bは塩基性では蛍光を発するcの構造に変化します。この変化は可逆的なので,再び酸性になると蛍光を発しなくなります。cの構造をもつ発光性のフルオレセインは,黄色の蛍光ペンの色素として日常的に使われています。