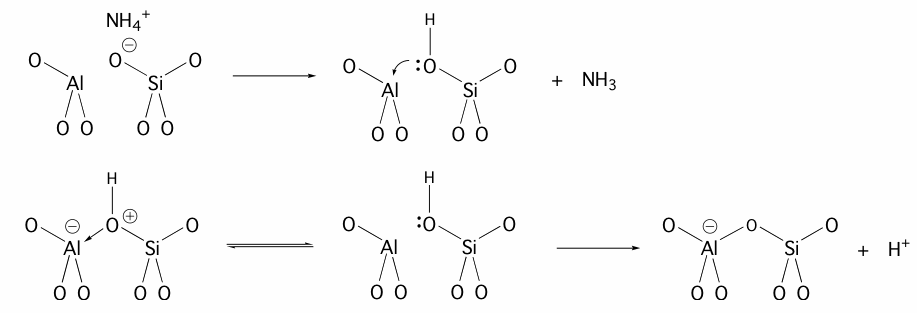ゼオライトはSiとAlの酸化物からなる物質で,アルミノケイ酸塩とかケイ酸アルミニウムなどとも呼ばれます。大きな表面積,分子の大きさ程度の規則的な細孔,陽イオン交換能を持つことが特徴です。下の図は,Yゼオライトの構造です。Yゼオライトは,ソーダライトケージと呼ばれるユニット6個からなる細孔を持っています。Yゼオライトではソーダライトケージ同士はケージの酸素六員環で接続していますが,酸素四員環で接続するとAゼオライトとなります
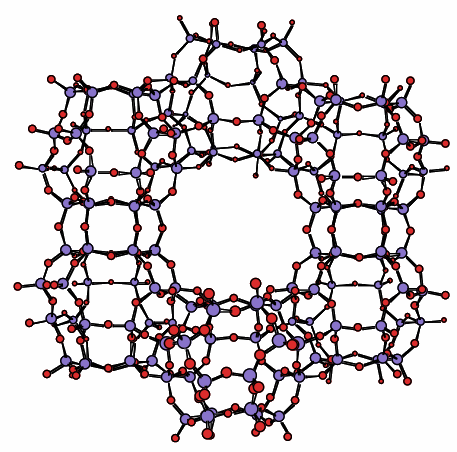
ゼオライトの結晶中でSiO2は四面体構造をとっています。このSiをAlで置換すると,Si4+でAl3+なので+1だけ電荷が足りなくなります。この電荷を補うために,Na+など交換可能な陽イオンが入ります。モレキュラーシーブスとして市販されているのは,Na+やK+でイオン交換したAゼオライトで,Na型とかK型と言います。Aゼオライトは,イオン交換しやすいゼオライトで,水の軟化剤として洗剤に含まれてます。
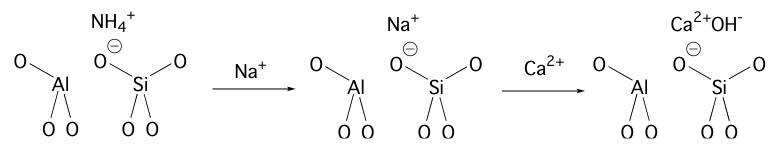
アンモニウム(NH4+)型のゼオライトを熱分解すると,NH3が脱離してプロトン型(酸型)になります。プロトン型ゼオライトは,強い酸性を示します。酸の強さはゼオライトの型で異なりますが,一般には,モルデナイト(MOR)>ZSM-5(MFI)>ベータ(BEA)>Y(FAU)となります。(括弧内はゼオライトの種類を表す記号で,アルファベット三文字で表すことになっています。)
市販のモレキュラーシーブス(MS)3AはK型,4AはNa型のAゼオライトです。MS4Aを硫酸銅溶液に入れ,Cu2+とNa+を交換すると,溶液中にNa+が出てきます。Cu型となったMS4Aをアンモニア水に入れると,Cu2+とアンモニウムイオンが交換し,溶液中に出たCu2+はアンモニアと錯体を作るため,溶液は青色に変化します。
イオン交換能はゼオライトの性質ですので他の種類でもイオン交換は起こりますが,Aゼオライトが最も速く,洗剤に含まれているAゼオライトでは交換は瞬時に起こります。
銅の代わりにコバルトを使っても同じ実験ができます。コバルトの場合,溶液は赤色となりますが,アンミン錯体は青色です。
実 験
(1)MS4Aを1 wt%硫酸銅溶液に浸す。容器に入れたMS4Aの倍の高さ程度溶液を入れる。
(2)時々かき混ぜながら,交換を行う。
(3)上澄み液の炎色反応を見る。4AはNa型なので,Naを確認。
(4)上澄みをデカンテーションで分離。蒸留水で数回洗浄する。
(5)蒸留水を加え,上澄みの炎色反応を見る。何も溶解していないことを確認。
(6)蒸留水とMS4Aが入った容器に,アンモニア水(1 N程度, 塩化アンモニウム溶液と炭酸ナトリウム溶液で代用可)を加える。徐々に青色に変化する。