合成高分子として高校化学では,ナイロン,ポリエチレン,ポリプロピレン,ポリ塩化ビニル,ポリスチレン,ポリエチレンテレフタラート,フェノール樹脂,尿素樹脂が取り上げられている。これらの高分子の主鎖(高分子の骨格)はC−C,C−O,C−Nの単結合からなっていて,不導体であることが共通した特徴です。
導電性高分子は電気を通すプラスチックのことで,白川英樹博士が作製したアセチレンフィルムを初めとして,ポリピロール,ポリアニリンなどがあります。導電性高分子は,CとCの結合(主鎖)において,単結合と二重結合が交互に連なった長い共役系を持っています。共役系高分子は,電子受容体を添加して電子を抜き取るとホール(正孔)が形成され,p型の導体となり導電性を示すようになります。
今回の実験では,塩化第二鉄(FeCl3)によりピロールの酸化縮合によりポリピロールを作製します。ポリピロールは,一般には電極での酸化によって作成されます。反応式は以下の通りです。
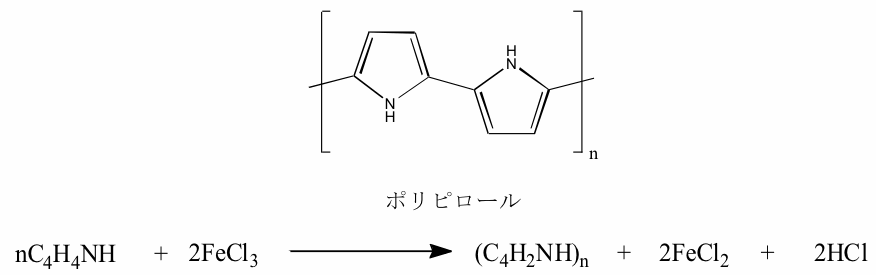
この実験では,ポリビニルアルコールを粘着剤として,塩化第二鉄をスライドガラス上にコーティングし,これにピロールの蒸気を接触させてポリピロールとします。塩化第二鉄は,酸化剤として働き縮合を起こすと同時に,ドーパント(電子受容体)として共役系から電子を引き抜く役割も持っています。このため,合成したポリピロールにはすでに導電性があり,灰色を帯びています。
試薬
塩化第二鉄,ポリビニルアルコール(洗濯のり),蒸留水,ピロール
塩化第二鉄は水溶液として使うので,含水物や長期間保存し吸湿したものでも構わない。ピロールは蒸気として使うので,変色したものでも構わない。
実験器具
スライドグラス,ビーカー,薬さじ,ピペット,試験管等,スターラー,ホットプレートなど,サンプル瓶等(スライドグラスが縦に入る容量),キムワイプ等,テスター等
実験手順
(1)塩化第二鉄100 mgを蒸留水10 mLに溶かし,スターラーで撹拌する。
(2)ポリビニルアルコール溶液5 mLを加えると,薄い茶褐色の粘性のある溶液ができる。(他の実験書より薄めになっています)
(3)溶液をスライドガラスにピペットで滴下し,ガラス棒などで薄く延ばす。
(4) ホットプレートの温度を100 ℃程度にしておき,スライドガラスを乗せて水分を蒸発させる。テスター等で導電性がないことを確かめる。(注意:水分を完全に除くと,ポリピロールが生成しなくなる。)
(5)サンプル瓶の底にキムワイプを敷き,ピロールを含ませる。スライドガラスを入れて立てかけ,変化を観察する。
(6)スライドガラスがポリピロールで灰色になったら取り出し,テスター等で導電性を確認する。
塩化第二鉄は,六水和物や長期間保存したもので構いません。濃度は,1〜5 %程度が適当です。
ポリビニルアルコール溶液の量は,スライドガラスから垂れない程度の粘性となるよう,適宜調節して下さい。
スライドガラスの乾燥段階で,水分が残っていると導電性を示すので,十分乾燥することが必要ですが,加熱を続けると酸化鉄で有機物が酸化され,黒色を帯びるので注意して下さい。
水分を完全に除くと,ポリピロールが生成しなくなります。
サンプル瓶は,シャーレ,ビーカーと時計皿,などで代用可能です。
テスターよりも,LEDを利用した導電性チェッカー(廣木氏(津山高専)提供)の使用が効果的です。
トランジスタは2SC1815,抵抗は1〜10kΩ,ボタン電池はCR2032です。